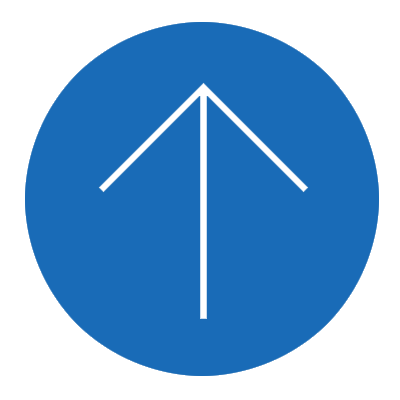【坂間】諏訪大社の特殊神事〜鹿の頭75頭分を供える“御頭祭”、その本来の意義は?
諏訪大社だけの特殊な神事。今回は、毎年4月15日に上社で行われる御頭祭について。鹿の頭を供える祭、とピンとくる方もいらっしゃるでしょうが、御頭祭は、本来そういう神事ではなかったのです。
〈御頭祭は、盛大な春の祭りの一部だった〉
御頭祭が、鹿の頭75頭分を供える様式になったのは、江戸時代です。では、それ以前はどうだったのか? 鎌倉時代や室町時代の文献などを元に説明します。
まず、御頭祭の正式な名称は、大御立坐(おおみたちまし)神事といい、旧暦3月の酉の日に行われます(だから、別名酉の祭といいます)。なお、御頭祭の“御頭”は、1年間、諏訪大社の神事に奉仕する当番の村=御頭郷(おんとうごう)の“御頭”が由来。頭を供えるからではありません。
さて、この神事は酉の日に行われますが、実は他にも神事があり、この日を含め13日間も続く盛大な春の祭でした。その中で、大御立坐神事は出発の儀式。出発の前に皆で直会(なおらい)をし、神様とともに食べ、お酒を飲む。これを神人共食といいますが、皆で食べるため鹿肉をたくさん集めました。鹿の頭は、大量に集めた証、神事の盛大さの演出です。そんなことを?と思われるかもしれませんが、皆さんも“鹿の頭75頭分”という文字だけで大いに興味をそそられているのですから、実際にその光景を目にすれば文句なく“諏訪大社はすごい”となったでしょう。ともあれ、それはあくまで賑やかし。神事の本義は、皆で鹿肉を食べること。なぜでしょう?

《お供えの鹿の頭の剥製:現在、十間廊で行われる御頭祭では、鹿の頭の剥製が祭壇に供えられます。》
〈実りのために、鹿の肉が必要だった〉
先ほど、大御立坐神事は出発の儀式と書きました。その後、大祝(おおほうり=上社の生き神様)の代わりに選ばれた子ども=神使(おこう)6名が、諏訪地域のあちこちにある湛(たたえ)と言われる所に向かいます。そこには巨木や巨石があり、それぞれで豊穣のために祈りを捧げました(これを廻湛神事といいます)。大御立坐神事を含む13日間の神事は、豊かな秋の実りのためにあったのです。
でも、なぜ豊穣の祈りに鹿肉が必要なのでしょう?
お話は、弥生時代に遡ります。稲作が始まり、農耕はより一般的になりました。しかし、当時の人たちは稲作を含む農耕は自然=神様に逆らう行為ととらえました(この思想は「古事記」のオオゲツヒメとスサノオのエピソードで暗喩)。神様に逆らえば、祟りがあるとも。恐ろしい祟りを避けるため、贄(にえ)=肉が必要と考えたようです。
では、鹿は? 鹿はなぜ? 室町時代の「年内神事次第旧記」には“鹿なくしては御神事はすべからず”と書かれていますから、かなり重要だったようです。これも、やはり弥生時代に毎年生え変わる鹿の角が稲の成長と実りのサイクルと一致したため、鹿は稲作の象徴とされたことが起源のようです。さらに、奈良時代の「播磨国風土記」には、鹿の血がまかれた土地に籾をまくと一夜にして苗が生えたというエピソードがあり、鹿と稲作の強い結びつきが伺えます。ただし、昔は食肉を“シシ”といい、これは鹿、猪の2つの獣を指しました。1356年の「諏訪大明神絵詞」では“禽獣(きんじゅう)の高盛り魚類の調味美を尽す”とあり、禽獣は鹿や猪などの獣や鳥のこと、さらに魚も可。また、江戸時代の「諏訪誌」でも同様で“鹿七十五に不足時は魚鳥を仮りてその数に賄う”とあります。重要なのは鹿肉ですが、皆で食べるために鹿をはじめ猪や鳥、魚の肉も用意されたようです。

《御頭祭の展示:神長官守矢史料館の御頭祭のイメージ展示。鹿はもちろん、猪の頭の剥製も展示されています。》
〈75頭という謎の数字〉
さて、最後に75頭の件。既に紹介した1356年の「諏訪大明神絵詞」、また室町時代の「年内神事次第旧記」では“高盛り”とのみ書かれています。江戸時代の1679年、上社の大祝の「上社社例記」では“七十余頭”。はっきり75頭と記されるのは、私が調べた限りでは1713年の貝原益軒の「木曽路之記」が最初。でも、その後も揺らぎます。1756年の「諏訪かのこ」では2カ所に記述があり、1カ所は“鹿七十七頭”、もう1カ所は“七十五頭”。1784年の菅江真澄の「諏訪の海」では“七十二”。寛政年間(1789〜95年)の「諏訪誌」は“七十五頭”。明治時代の1886年の「信濃奇勝録」は“猪鹿の頭七十五”と2カ所に記述。どうやら75頭の表記は江戸中期以降のようです。
なお、75という数字は他の神社や地域の神事や習俗でも登場します。75膳とか、人の噂も75日もそうで、1つの様式のようです。しかし、75がどういう意味なのか、よくわかっていません。季節の区切り、農作物の収穫時期、終わりや果ての意味、神話や仏教に由来等々。一説には、たくさん、数多くという意味もあるようです。
実は、13日間の春の祭は中世以降に廃れ、江戸時代前には簡略化されて大御立坐神事部分だけが行われていたようです。本来の意義は失われましたが、大御立坐神事では、まだ大量に鹿肉を必要としていました。その目標値としてあいまいな“70余頭”という表現から、様式を重んじて明確でかつ大量を表す “75頭”という表現に変わったのかもしれません。

《峰の湛のイヌザクラ:御頭祭の後、神使が祈りを捧げるために出向いた湛。唯一、巨木が残る峰の湛。》
〈諏訪大社の長い歴史の中で〉
長くなってしまいました。タイトルにした鹿の頭75頭分を供える御頭祭の一文は、江戸時代中期から明治時代までの様式。それ以前、鎌倉時代は大御立坐神事=御頭祭を含む13日間の春の祭で、鹿肉等を神様と共に皆でいただき、秋の豊作を祈って諏訪の中を廻る重要な農耕の神事でした。3月というとまだ寒そうですが、新暦では4月の中旬ごろにあたります。二十四節気では穀雨=田植え等を始めるころで、豊穣の祈りにはちょうどいい時期。いろいろ不明点もありますが、神事の次第は古い信仰、思想に基づく様々な理由があってのことです。
諏訪大社は長い歴史を持っています。神事も長い時間の中で変化し、その内容も移り変わりました。中には完全に途絶えてしまった神事もあります(以前書いた御室神事等)。そんな中、御頭祭は変容こそしましたが、古代からの思想や信仰を感じさせる神事として今もあります。それが何よりも貴重な文化遺産で、ありがたいと思うのです。野蛮などと言われますが、それは現代の合理にとらわれているだけ。私たちの祖先の切実な祈りと、そこから生まれた伝統文化やその多様性に想いが至っていないのでは?と思えてなりません。むしろ、自然と人との関係を見直すきっかけになるのではないでしょうか。
※掲載の内容については諸説あります。
参考文献:「復刻版諏訪史料叢書」第一巻:年内神事次第旧記、諏訪大明神絵詞、社例記(上社)大祝本他、「肉食の社会史」山川出版社など。