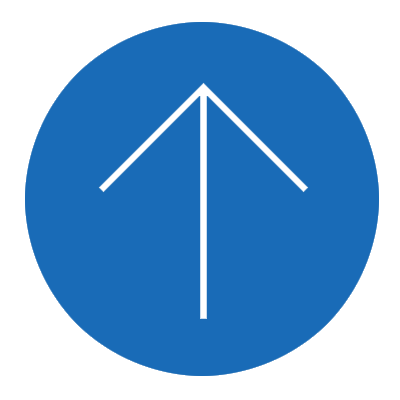【坂間】諏訪大社下社、遷座祭(せんざさい)の謎。
諏訪大社は上下社があり、それぞれ2社で計4社。今回、お話しする下社は、春宮と秋宮の2社になります。この2つのお社では、昔から年2回、遷座祭が行われていました。遷座というのは、神様が遷(うつ)ること。2月1日は秋宮から春宮へ、8月1日は春宮から秋宮へ、御霊代(みたましろ)が御輿に乗って移動します。1年の間で定期的に遷座祭を行うのは、かなり特殊。なのですが、これもまた、なぜ、なんのため?という謎が。

《冬の遷座祭(2016年2月1日)》

《夏の遷座祭(2023年8月1日)》
*昨年2024年8月1日遷座祭の模様(通称「お舟祭り」)はこちら。
諏訪大社では、遷座祭を農耕に関わる祭としています。こちらについて、もう少し補足したいと思います(わかる範囲で)。
日本各地の伝承にこんなものがあります。
〜春、山の神様が里に降りて田の神様になる。秋には山に登り、山の神様に戻る〜
これが下社に春宮と秋宮の2社があり、年に2回、遷座する理由と考えられています。秋宮から春宮への遷座が“山の神様が里に降りて田の神になる〜”に当たり、春宮から秋宮への遷座が“田の神が山に還る〜”に当たるとされます。
でも、秋宮が鎮座するのは山ではありません。田の神様が還る山は、おそらく本来は下社の背後の霧ケ峰。中でも八島ケ原湿原が重要と考えられています。こうした湿原は、青々と生えている草がちょうど稲のように見えるため、神様の田んぼと呼ばれ、古代から祭祀が行われてきました。同じ長野県の苗場山にも湿原があり、神様の田と考えられて、農耕の神様を祀っていたようです。

《八島ケ原湿原。八島は、古代の日本の異名。多くの島の意味も。》
画像の八島ケ原湿原も田んぼのように見えませんか。また、ここには下社と関わりのある旧御射山社(もとみさやましゃ)があり、奥社のように考えられています。

《旧御射山社。かつてはここで大規模な祭が行われました。》
文献が残っていないため、先の“山の神〜田の神”の伝承がどういう経緯で春宮と秋宮間の遷座になったのか、現状は不明です。以前の坂間ブログをご覧になられた方はまたか、と思われるでしょうが、はい、また不詳です。しかし、下社と八島ケ原湿原が断ちがたい関係にあることは明らかです。
いずれ、日本のどこかで新たな文献や史料が見つかり、春宮と秋宮の謎、遷座祭の不思議についても明らかになるかもしれません。“山の神が〜”という伝承を元にした仮説が正しいのか、まったく違う理由なのか、はたして? その日を楽しみに待ちたいと思います。
※掲載の内容には諸説あります。