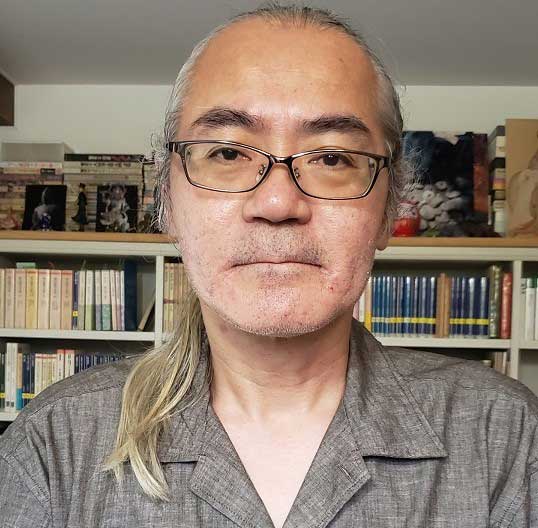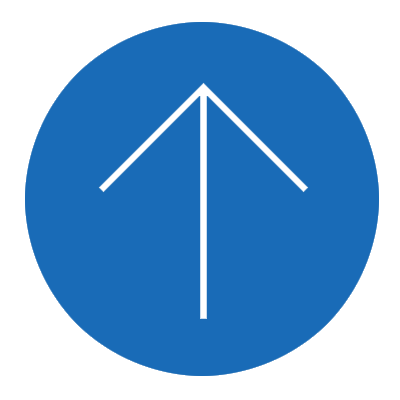【石埜】「歴史と地勢からみる古寺」〜①松本・塩尻編(真言宗寺院巡礼ツアーに寄せて)
先日(2025年8日4日)告知を開始して、参加者募集中の「真言宗寺院巡礼ツアー」。長く地域に根付いたお寺を訪れ、密教修行「受戒」「瞑想」「護摩」を体験いただくツアーです。
今回のブログでは9月23日①松本・塩尻編で巡る寺院について、ガイドの石埜がその魅力と特徴を詳しくご紹介します。
松本平の南部は、深志(松本城周辺)方面から木曽、伊那、諏訪へと分岐する古くからの要地です。史跡や古刹も数多く、山沿いを中心に江戸時代の趣を残す美しい村が点在しています。幹線道路をちょっと離れれば、あなたの知らない世界が広がっているのです。
◆郷福寺
今はワインの銘醸地として知られる桔梗ヶ原ですが、かつては松本平南部の氾濫原全体を指していたようで、郷福寺はそのただなかに位置します。広大な原野は徒歩で移動する昔の旅人にとっては砂漠のようなもの。中世においては松本の小笠原勢力と諏訪勢力との緩衝地帯でもあり、幾度も大きな戦の舞台となりました。江戸時代に至って善光寺街道が整備され、郷原宿が置かれます。その中心で精神的拠り所となったのが郷福寺です。今も残る宿場町の風景の中、「町場のお寺」に特有の風格が門前から漂ってきます。
 1
1 2
2 3
3 4
4
 5
5
《1.郷福寺境内 2.宿場町の面影を残す郷原宿の一角、郷福寺の近くに今も建つ高札 3.郷福寺の入り口付近にある明治天皇御巡幸の際「御膳水」を取ったとされる井戸 4.郷原街道沿いに建つ大寺院郷福寺を臨む 5.山門》
◆宝輪寺
松本市今井は、桔梗ヶ原と、古村の並ぶ西山との中間に位置する村。木曽義仲四天王で高名な今井兼平が、ここを拠点とした伝えがあります。小笠原と諏訪の対立が深まる時代、木曽谷の入口を固めるこの地にいた今井氏は、一族で諏訪へと移住。諏訪勢力と今井氏の間には、義仲時代からの結束がありました。現在、諏訪地方の岡谷市に今井という村があるのは偶然ではないのですね。今井氏は今井に住んでそう名乗ったということですが、それが岡谷に移住すると、今度は地名が今井になる。不思議に思えますが、それだけの名族だったということ。古村の中心にどっしり構える宝輪寺は、今井兼平中興と伝えます。
 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10
《6.宝輪寺仁王門から鐘楼門を臨む 7.本堂 8.厄除大祭(1月)本堂 9.厄除大祭(1月) 観音堂 10.観音堂》
◆古川寺
朝日村、西洗馬から古川寺のある古見に至る山沿いには、趣深い山村の風景が続いています。中世には洗馬荘と呼ばれ、木曽義仲伝承も残る歴史ある土地。寺の下を通り、桔梗ヶ原から安曇野市の住吉までを結ぶ道路は現在「サラダ街道」の愛称で親しまれていますが、一目見れば古道とわかるでしょう。山裾から村を見守る古川寺も、平安時代創建の由緒を伝える古刹。背後の山上にある清水寺とも関係が深く、古き山岳信仰の気配も漂います。廃仏毀釈が激しかった松本の平にあって、ここは高遠藩に属していたため昔姿をそのままに留めることができました。
 11
11 12
12 13
13
 14
14 15
15 16
16 17
17
《11.古川寺鐘楼堂を臨む 12.鐘楼堂 13.本堂 14.庫裡 堂々たる古民家建築 15.庫裡の玄関 16.庫裡の天井 17落人を匿ったともされる部屋に続く隠し階段》
松本・塩尻編の3つの寺院は、どれも古くからあるコミュニティをずっと支えてきた古拙。それぞれの村、街の雰囲気を味わいながら、積み重なった歴史と今もそこに集う地元の人たちの想いをしっかり感じ取っていただければと思います。
→3つの寺院を巡るツアーの詳細、ご予約はこちら