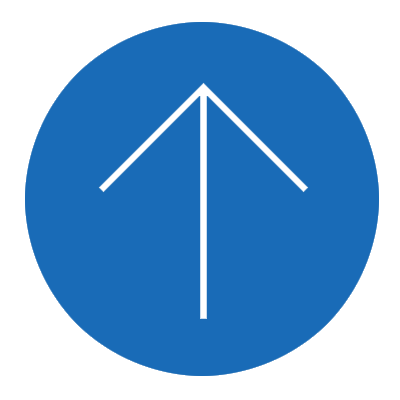<ツアーの流れ>
- 少年ジャンプ連載『逃げ上手の若君』に、取材アテンド、諏訪関係の解説執筆等で協力した石埜三千穂本人がガイド。石埜はおたく業界での職歴があり、長年にわたる漫画好きでもあります。取材時のエピソードなど、裏話も?
- 時行は、どうしてわざわざ諏訪〜南信州に? 文化的、歴史的背景を、楽しく、わかりやすく解説します。漫画やアニメをきっかけとして、諏訪〜伊那谷地域の歴史の面白さ(特に中世/南北朝)に触れてみてください。
- お昼は宗良親王に縁の深い平福寺にて、地元の名店「神楽」特製、季節感、郷土色豊かなお弁当をいただきます。

【諏訪大社上社前宮】諏訪の領主にして現人神である「大祝」(おおほうり)、つまり諏訪頼重が居住していた聖地。作中、初めて諏訪に着いたシーンの背景はこのお宮の入り口です。つまり、物語前半、彼らが暮らしていたのがここ。伝・頼重供養塔などを見学し、本殿に参拝します。

【諏訪大社上社前宮】かつては鹿の首75頭分を並べたという御頭祭(おんとうさい)、別名・酉の祭(とりのまつり)の祭場である十間廊。右側の格子がはまった部分が大祝の御座所です。『鹿の国』で再現した神事芸能の舞台、冬の間だけ祭場として建てた「御室」もこの付近にありました。

【乙事諏訪神社】(おっことすわじんじゃ)高原の村の森の中に佇む、知られざる名社。諏訪大社の御分社で、社殿は旧・上社本宮拝幣殿を江戸時代に移築したもの。中世の様式が随所にみられる瀟洒な社殿で、国重要文化財に指定されています。

【乙事諏訪神社】(おっことすわじんじゃ)取材時、「中世建築がみたい」という作家さんの要望に応え石埜がこの社殿を紹介し、諏訪大社社殿を描く際のモデルとして採用されました。また、作中で神党が掲げる独特の梶の葉紋も、実はここに原型があります。

【平福寺】時行と共闘した宗良親王の護持仏と伝える阿弥陀如来像を守る古寺。隣接する正八幡宮は宗良親王が仮宮としたという伝承を持ち、平福寺はその別当寺(神仏習合時代、神社と一体でその祭神を仏式で祀っていた寺院)でもありました。

【平福寺】同じお堂の中にもう一体、等身大の立派な阿弥陀如来像があります。鎌倉時代、最盛期の慶派(運慶に始まる名門の流派)仏師の手になるもので、長野県宝。これだけ立派な仏像が諏訪にある理由として、北条家との深い結びつき抜きには考えられません。

【平福寺 おひぎりさま会館にて昼食】参拝者の休憩所、交流の場でもあるこちらで昼食をいただきます。毎月23日のおひぎりさま(日限地蔵尊)縁日には、ここで大黒さま(お寺の奥様)手づくりの暖かいそうめんやお菓子が提供されます。

【平福寺 おひぎりさま会館にて昼食】諏訪大社下社秋宮前の名店、二十四節気神楽の武居さんによるお料理をいただきます。

【八幡宮(柴宮)】岡谷市東堀区の町中に鎮座する、深い社叢に囲まれた静かなお宮。「柴宮」の別名は仮宮を意味し、宗良親王の仮御所があったとの伝承に基づくものです。乙事諏訪神社にも似た諏訪社風の社殿ですが、軒には菊の御紋が輝いています。

【八幡宮(柴宮)】氏子さんたちは宗良親王への信仰を大切に守り続けてきました。ここでは、宮司さんから宗良親王との御縁について、逃げ若の内容も踏まえたお話をお聞きします。

【常福寺】時行と宗良親王が小笠原軍と対峙した大徳王寺城の戦い、その旧跡に建つ曹洞宗のお寺。大徳王寺というお寺についてはまったくわかっておらず、作中でも廃寺の遺構を利用して築城したという話になっています。

【常福寺】本堂の裏に、僧形の宗良親王像が祀られています。昭和15年5月12日、天井裏から落ちてきたという奇跡のような像で、天台座主(天台宗のトップ。出家した皇族が名誉職的に就任する例がある)だったころの親王を表したものとされています。

【宗良親王供養塔】これも明治時代中頃に発見されたという卵塔(僧侶の墓の形式)で、宗良親王の皇子、尹良親王が建てたという銘と、菊の御紋が確認されたといいます。地元では「御山(みやま)」と呼んで手厚く祀っており、今も地元のコミュニティが主催し、常福寺で毎年春秋年2回の法要が執り行われています。

【大徳王寺城跡】 農地化しているためはっきりしませんが、郭や堀切と思われる地形が確認できます。なるほど眺めの良い場所で、今は美和ダムとなっている三峰川の深い谷を挟み、対面の山地に小笠原貞宗の軍が陣を張っていた様子が目に浮かんできます。